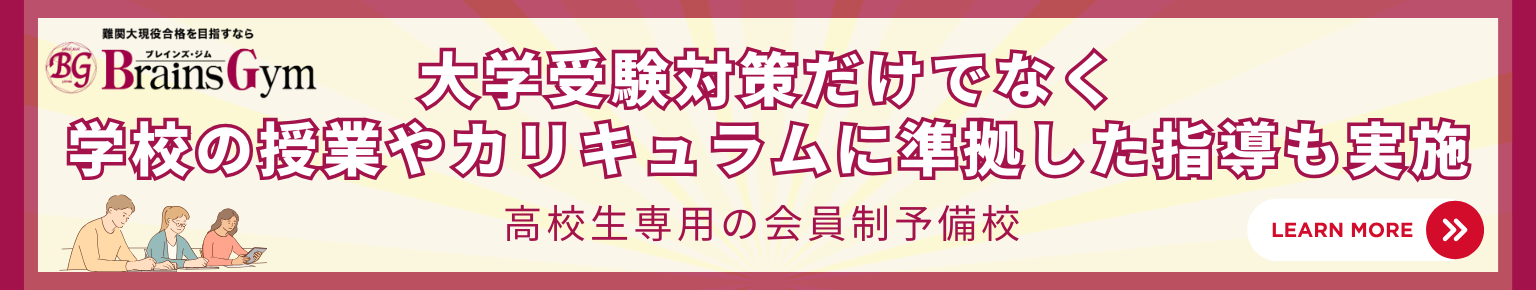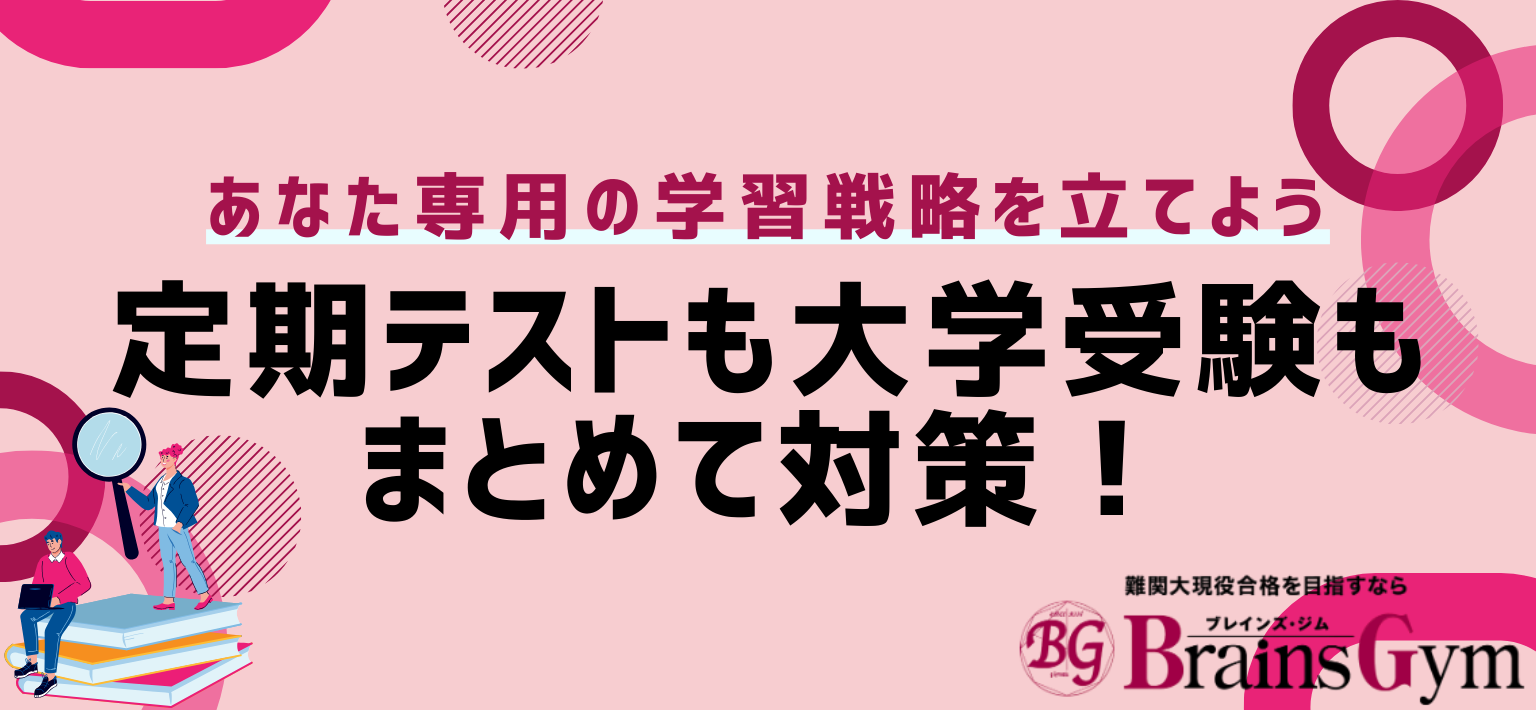2025.05.30
定期テスト対策のコツとは?基本と結果を出す効率的な勉強法をご紹介!
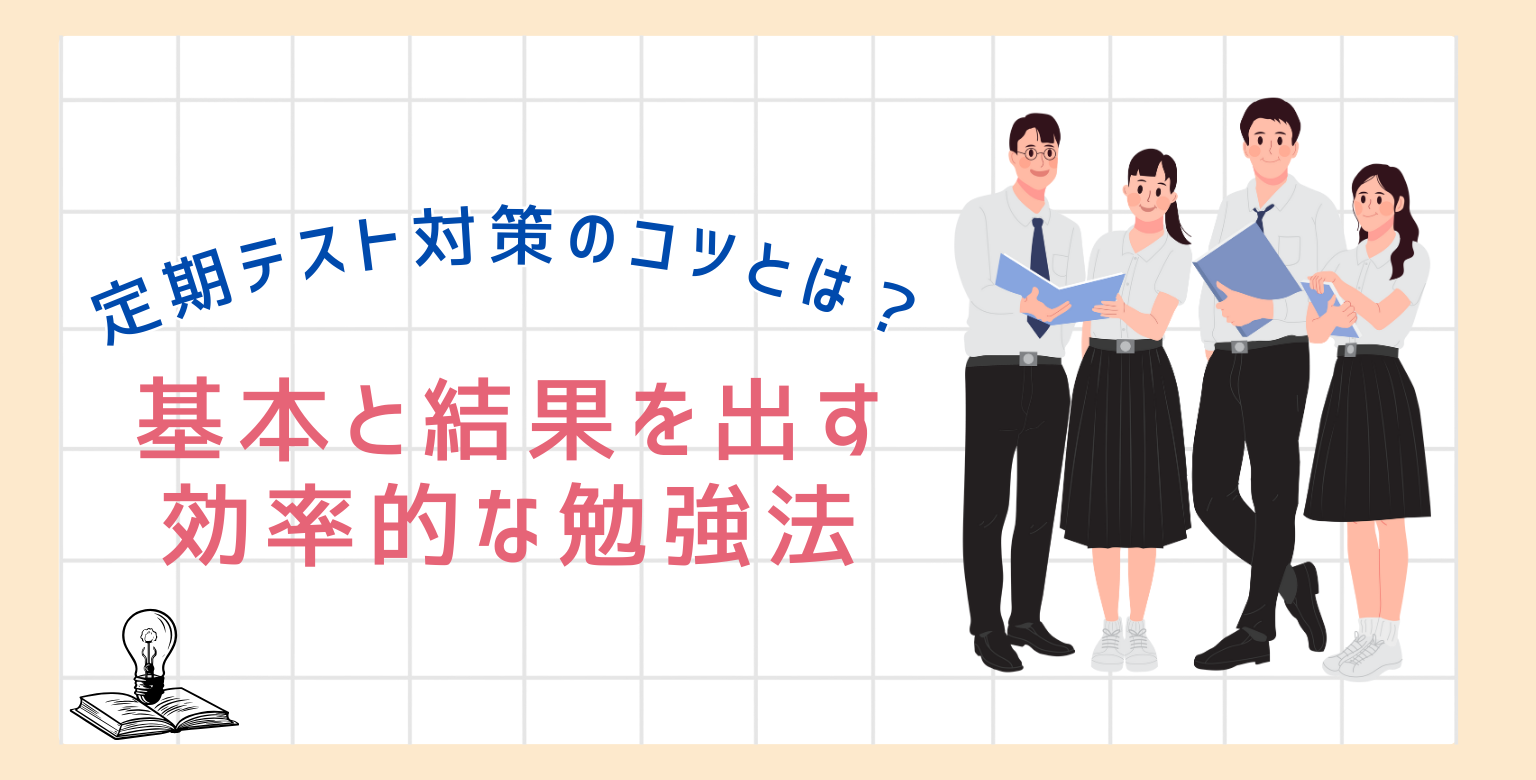
「定期テスト対策って何から始めればいいんだろう」「効率よく点数を上げる方法が知りたい!」そんな悩みを抱えていませんか?
定期テスト対策では、やみくもに勉強するのではなく、テスト範囲を把握し、優先順位をつけて取り組むことが成功への近道です。
本記事では、定期テスト対策の基本的な進め方や、効果的な勉強法についてご紹介します。
高校の定期テスト対策が重要な理由
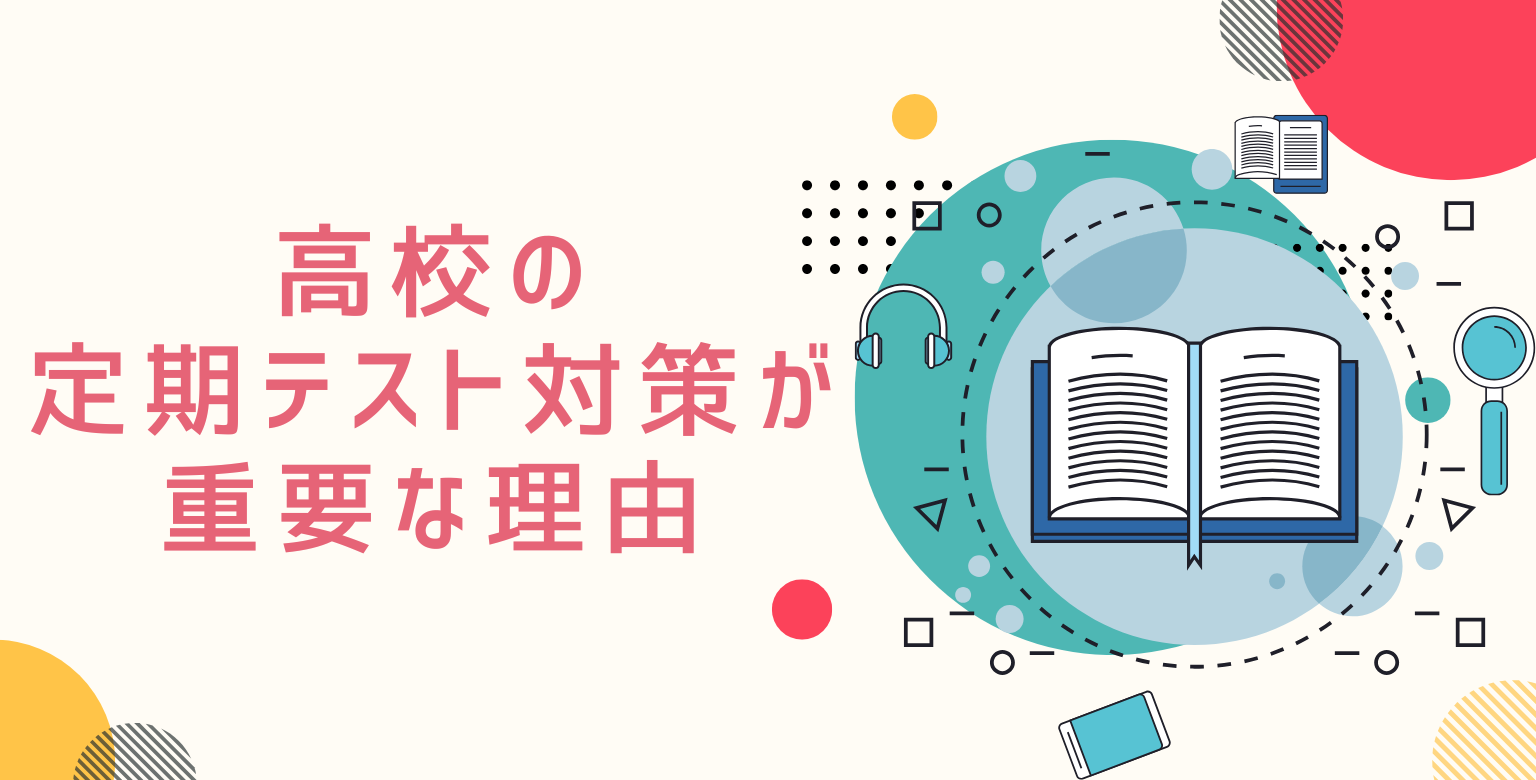
高校生活の中でも、定期テストは特に重要な位置を占めており、単に成績をつけるためだけのものではなく、将来の進路や学力形成に直結する大切な機会です。
しっかりと定期テスト対策に取り組むことで、学習習慣が身につき、学校推薦型選抜や総合型選抜で有利になるだけでなく、大学受験に向けた基礎力をしっかり固めることができます。
ここでは、なぜ高校の定期テスト対策がそれほど重要なのかを、具体的な3つの視点から詳しく解説していきます。
学習習慣の形成
高校の定期テスト対策は、単にテストで良い点を取るためだけでなく、自ら計画を立て、日々の勉強に取り組む習慣を身につける絶好の機会です。
定期テストは数か月ごとに必ず行われるため、このサイクルの中で「計画→実行→振り返り」という学習リズムを体得することができます。
計画を立て、コツコツと勉強を進める経験を繰り返すことで、「目標を設定し、それに向かって努力する力」が自然と養われます。
この学習リズムが定着すれば、受験勉強はもちろん、大学生活や社会に出てからも大きな武器になります。特に高校時代は、勉強以外にも部活動や行事で忙しいため、自分で時間を管理しながら学習を進める力が求められます。
定期テスト対策を通じて、自己管理能力や粘り強く取り組む姿勢を育てることが、将来にわたっての成功の土台となります。
学校推薦型選抜・総合型選抜への影響
近年、一般入試だけでなく、学校推薦型選抜や総合型選抜を目指す生徒が増えています。これらの選抜方式では、学力試験だけでなく、日頃の成績を示す「評定平均」が重視されます。
この評定平均は定期テストの結果に大きく影響されるため、普段から安定して高得点を取ることが非常に重要です。いくら模試で良い結果を出していても、学校の成績が伴わなければ、推薦のチャンスを逃してしまうこともあります。
学校推薦型選抜や総合型選抜を視野に入れている場合は、定期テスト対策をおろそかにせず、将来の進路の幅を広げるためにも、着実に対策を進めていくことが求められます。
大学受験の基礎固め
高校の定期テストは、大学受験に必要な基礎学力を身につけるための絶好の機会です。
受験勉強は高校3年生になってから本格化するイメージがありますが、大学受験の問題は、約8割が1・2年生の内容から出題されるため、1・2年生のうちにどれだけ基礎を固めておけるかが、合否を大きく左右します。
定期テストの範囲は、教科書や授業内容をもとに構成されており、受験に直結する重要な知識ばかりです。特に主要教科(英語・数学・国語)は積み重ねが重要であり、穴があると後々苦労することになります。
この段階で一つひとつ確実に理解し、自分のものにしておくことで、高校3年生になったときに応用問題への対応力が格段に高まります。
定期テストを「目先の成績」だけで捉えるのではなく、「大学受験のための基礎固め」と位置づけ、着実に積み上げることで、ブレない学力を養い、受験本番に向けた大きな自信にもつながります。
【定期テスト対策】スケジュール作成の基本ステップ
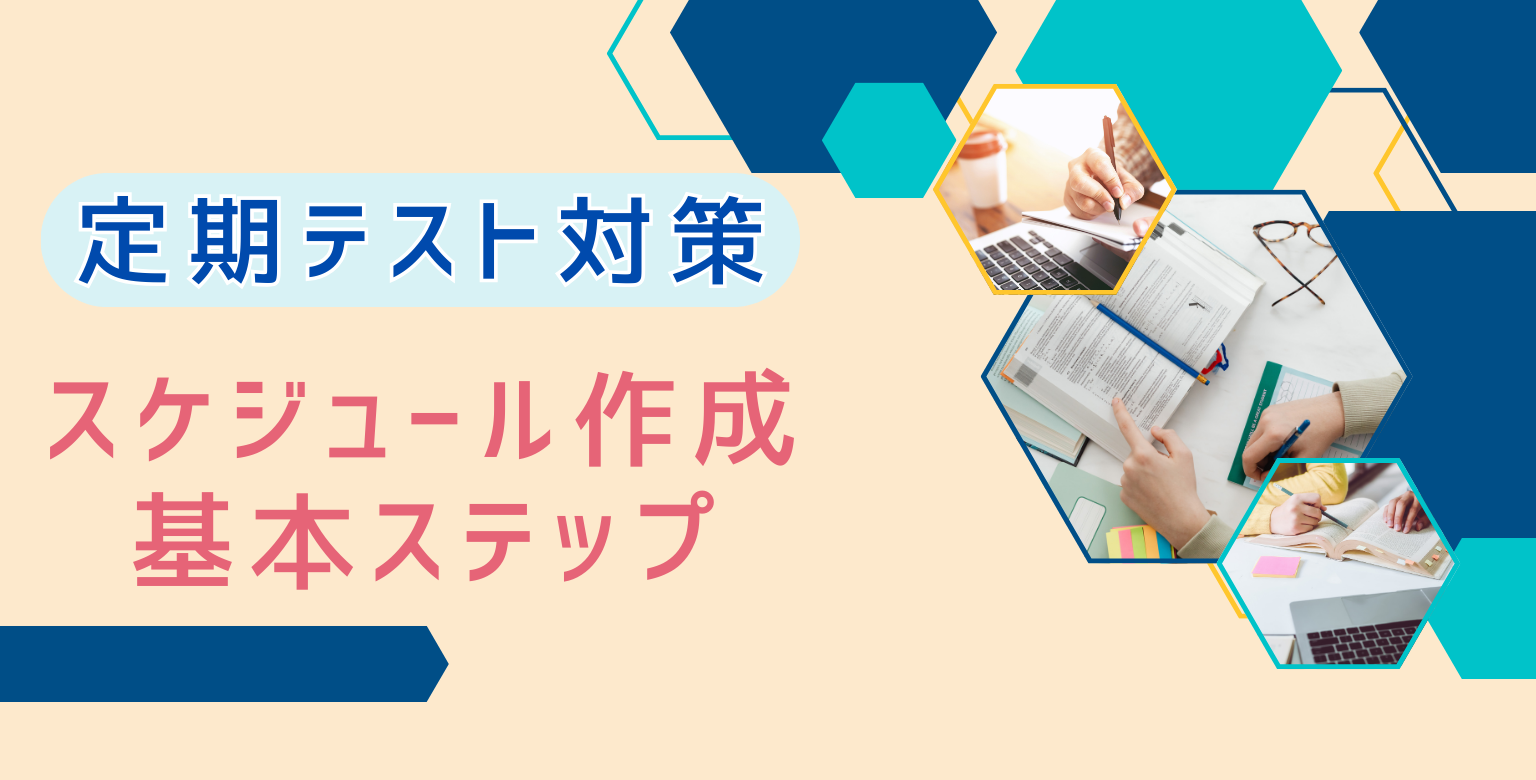
定期テストで結果を出すためには、ただやみくもに勉強するだけでは不十分です。限られた時間の中で効率よく学習を進めるには、しっかりとしたスケジュール作成が欠かせません。
計画を立てずに勉強を始めてしまうと、時間が足りなくなったり、重要な範囲に手をつけられなかったりすることもあります。
ここでは、失敗しない定期テスト対策のために、誰でも実践できるスケジュール作成の基本ステップを、ポイントを押さえてわかりやすく解説します。
テスト範囲を確認する
まずスケジュール作成の第一歩は、正確なテスト範囲の把握です。テスト範囲が曖昧なままでは、対策の立てようがありません。
学校から配布される範囲表や先生からの指示をもとに、どの教科のどこからどこまでが対象なのか、しっかり確認しましょう。
範囲だけでなく、強調されたポイントや「ここが出るよ」と言われた部分も、忘れずにメモしておくとベストです。もし曖昧な点があれば、早めに先生や友達に確認しておくことも大切です。
テスト範囲を把握することで、必要な学習量や優先順位が明確になり、効率的なスケジュール作成につながります。
この工程をおろそかにすると、せっかく努力しても得点に結びつかないという事態になりかねません。
残り日数を把握する
次に重要なのは、テストまでの残り日数を正確に把握することです。
「まだ時間がある」と油断していると、あっという間にテスト前日になってしまうので、カレンダーを使ってテスト本番までの日数を数え、具体的なイメージを持ちましょう。
また、各教科ごとの試験日が異なる場合は、それも意識しておく必要があります。さらに、部活や学校行事などで勉強できない日も考慮に入れておくと安心です。
使える日数がはっきりすると、1日に必要な学習量も自然と見えてくるため、ゴールまでの距離を把握することで無理のないペース配分ができ、精神的にも余裕を持って取り組めるようになります。
やるべきことを書き出す
テスト範囲と残り日数を把握したら、次はやるべきことをリストアップしましょう。
例えば、「数学の教科書P50〜80を解く」「英語のUnit4単語暗記」「国語の漢字練習30個」など、具体的なタスク単位で書き出すことがポイントです。
ここで大切なのは、曖昧な表現を避けることです。
単に「英語の勉強」とするのではなく、「英単語20語暗記」「長文問題を3問解く」といったように細かく分けることで、1日の達成目標が明確になります。
やるべきことを見える化することで、取り組むべき優先順位も整理しやすくなり、勉強に対するモヤモヤ感がなくなります。また、目に見えるリストがあると、達成感も得られるため、モチベーションアップにもつながります。
1日のノルマを決める
やるべきことが整理できたら、それを1日のノルマに分割していきましょう。例えば、数学の問題集が30ページある場合、残り10日間で3ページずつ進めるといったように、現実的にこなせる分量を設定することがポイントです。
無理なノルマを立てると、達成できなかったときにモチベーションが下がってしまいます。部活や予定がある日はノルマを軽くするなど、生活リズムに合わせた柔軟な設計を心がけましょう。
1日のノルマがはっきりしていると、毎日「何をやればいいか」で迷うことがなくなり、勉強にすぐ取りかかれるようになります。
着実にノルマをクリアすることで、自信と達成感を積み重ねられます。
具体的なスケジュールに落とし込む
最後に、決めたノルマを時間帯ごとの具体的なスケジュールに落とし込みます。
例えば、「19:00〜19:30 英単語暗記」「19:30〜20:30 数学問題演習」「20:30〜21:00 理科の復習」といった具合に、時間ごとに勉強内容を細かく割り振ります。
特に、帰宅後から寝るまでの時間や、学校の昼休み、移動時間などの隙間時間も有効活用できるように意識しましょう。具体的な時間割を作っておくことで、勉強と休憩のメリハリがつき、ダラダラせずに集中して取り組めるようになります。
また、スケジュールに多少の余白を持たせておくことで、予定外のトラブルにも柔軟に対応できる安心感が生まれます。
【定期テスト対策】効率的な計画に必要な「3つの視点」

どれだけ丁寧にスケジュールを立てても、実際に効果が出なければ意味がありません。
定期テストでしっかり成果を上げるためには、ただ計画を作るだけでなく、「効率よく実行できる工夫」が必要です。
ここでは、計画作成時に押さえておきたい「3つの視点」について具体的に解説していきます。
優先順位を決める
すべての教科を同じように勉強しようとすると、時間も労力も分散してしまい、どれも中途半端になりがちです。限られた時間を最大限に活かすためには、優先順位を明確にすることが大切です。
例えば、苦手科目や配点の高い科目、前回のテストで点数が振るわなかった科目などは、早めに手をつけ、重点的に時間を割くようにしましょう。
一方で、得意な科目やすでに理解が進んでいる分野については、短時間で効率よく復習する形で進めてみてください。取り組む順番を戦略的に決めることが、結果を出すための近道です。
復習時間を必ず確保する
一度覚えたと思っても、時間が経つと忘れてしまうのが人間の脳の特徴です。そのため、学習した内容を記憶に定着させるには、復習が欠かせません。特に重要なのは、「学習直後」「翌日」「1週間後」など、時間を空けて複数回にわたって復習を入れることです。
このサイクルを意識するだけで記憶の定着率が大きく向上するため、スケジュールを立てる際は、復習の時間を最初から組み込んでおくことがポイントです。
「今日は新しい範囲を勉強」「明日はその復習」など、計画に緩やかな反復のリズムを持たせることで、理解の深さと記憶の持続力が格段にアップします。
短期記憶で終わらせず、しっかり自分の力に変える学習を意識しましょう。
余白を持たせる
スケジュールをきっちり詰め込みすぎると、少しの予定変更や体調不良で崩れてしまい、結果的にやる気を失ってしまう原因にもなります。そのため、あらかじめ「余白」を持たせておくことが重要です。
例えば、1日の中で少し空き時間を確保したり、週末に“予備日”を設定しておいたりすることで、うまく調整が効くようになります。
また、余白の時間は、復習や振り返り、気分転換などにも活用でき、無理なく計画を進めるうえでの潤滑油となります。
完璧なスケジュールを目指すのではなく、継続できるスケジュールを目指すことが成功への鍵となるので、心にも時間にも余裕のある計画で、安定した学習リズムを築きましょう。
【定期テスト対策】教科ごとのスケジューリングのコツ
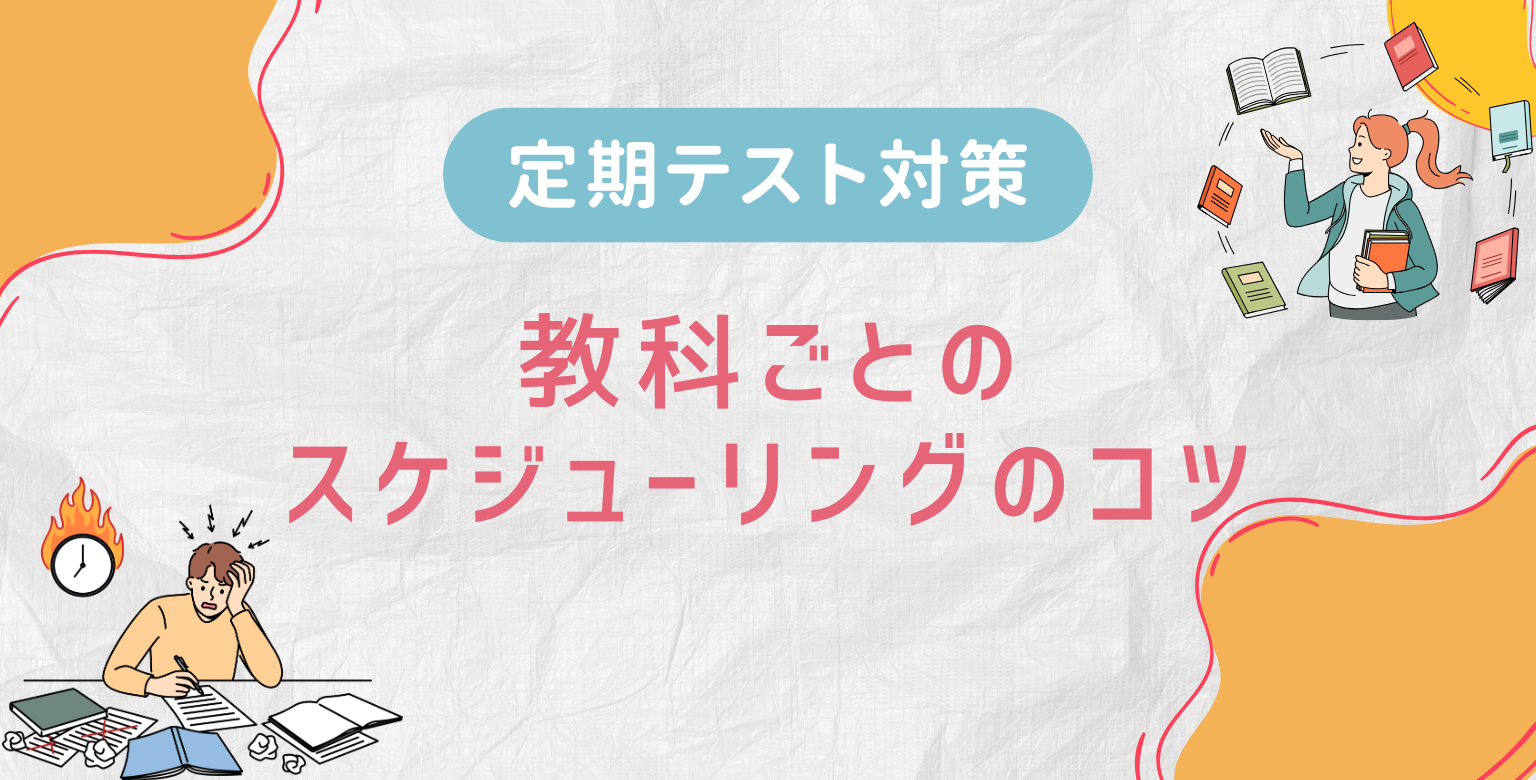
定期テスト対策で成果を上げるためには、教科ごとの特性を理解し、それに応じたスケジューリングを行うことが重要です。
各教科の特性に応じてスケジュールの組み方を工夫することで、学習の効率は格段に向上します。自分の得意・不得意を把握したうえで、無理なく続けられるプランを立てましょう。
ここでは、それぞれの教科に適した学習方法と時間配分について解説します。
英語
英語は「単語」「文法」「長文読解」など、学習の柱が複数あるため、項目ごとに分けてスケジューリングすることが大切です。
単語暗記は一気にやるよりも、毎日少しずつ繰り返すほうが定着しやすいため、「1日20語」など、具体的な数を決めて取り組みましょう。
文法問題は演習中心に、問題集を1日1ページずつ解くなど、地道な積み重ねが効果的です。長文読解は集中力が必要なので、比較的元気な時間帯(放課後すぐや早朝)に設定するのがおすすめです。
1日ごとに学習テーマを切り替えるのではなく、「毎日少しずつすべてに触れる」設計が、英語力全体の底上げにつながります。
数学
数学は「理解→演習→見直し」という流れがとても重要です。まず、苦手な単元や頻出分野から優先的に取り組みましょう。
新しい内容を学ぶ際には、授業のノートや解説動画などを活用して基本をしっかり押さえたうえで、問題演習に取りかかると理解が深まります。
演習の時間は毎日確保するようにし、特に「わからなかった問題」や「正解したけれど曖昧な問題」は必ず印をつけて、後日もう一度取り組む時間をスケジュールに組み込んでおくと効果的です。
また、テスト直前には過去問や予想問題に挑戦することで、実戦力も養えます。得意・不得意に応じて難易度を調整しながら、徐々にステップアップしていく計画を立てるのがコツです。
国語
国語は「現代文」「古文」「漢文」のそれぞれに特化した対策が必要です。
現代文は意味段落ごとに自分で要約し、板書と見比べて正しく読解できているか確認しましょう。古文・漢文は暗記要素が強いため、文法や重要単語、句形などを短時間で反復できるようにするのがポイントです。漢字については、日々少しずつ練習時間を取ることで、確実に得点源になります。
国語は「何となくできる」と思われがちですが、計画的に読解練習を積まないと本番で点が伸びにくい教科です。メリハリを持って「暗記」と「思考」の両面に取り組むスケジュール設計を意識しましょう。
理科
理科は「暗記+計算問題」という二つの特性を持つため、学習内容によってやり方を使い分けることが大切です。
生物・地学など暗記中心の分野では、語句や原理をノートにまとめ、短い時間で何度も見直すようにしましょう。一方、物理や化学など計算が必要な分野では、公式の意味を理解したうえで演習を重ねることが必要です。
特に問題を解く練習では、1問ずつ丁寧に手を動かす時間を確保するのが効果的です。さらに、グラフや図解の読み取りに慣れておくことも重要です。
理科は範囲が広いため、単元ごとのスモールステップで計画を立てることが成功のポイントになります。
社会
社会科目は暗記が中心ですが、単なる「丸暗記」ではなく、流れや因果関係を理解しながら覚えることが重要です。
日本史や世界史の場合は、年表や人物相関図を使ってストーリーとして覚えると記憶に残りやすくなります。
地理や公民は統計や制度などが問われるため、資料問題にも取り組み、インプットの時間だけでなく、アウトプットの機会を必ず設けることが大切です。
例えば、一問一答形式の問題を使って、短時間で自分の理解度をチェックする時間を毎日10〜15分でも入れることで、学習効率が格段にアップします。スキマ時間を活かした反復が、得点アップの鍵です。
【定期テスト対策】よくある失敗例とその回避法
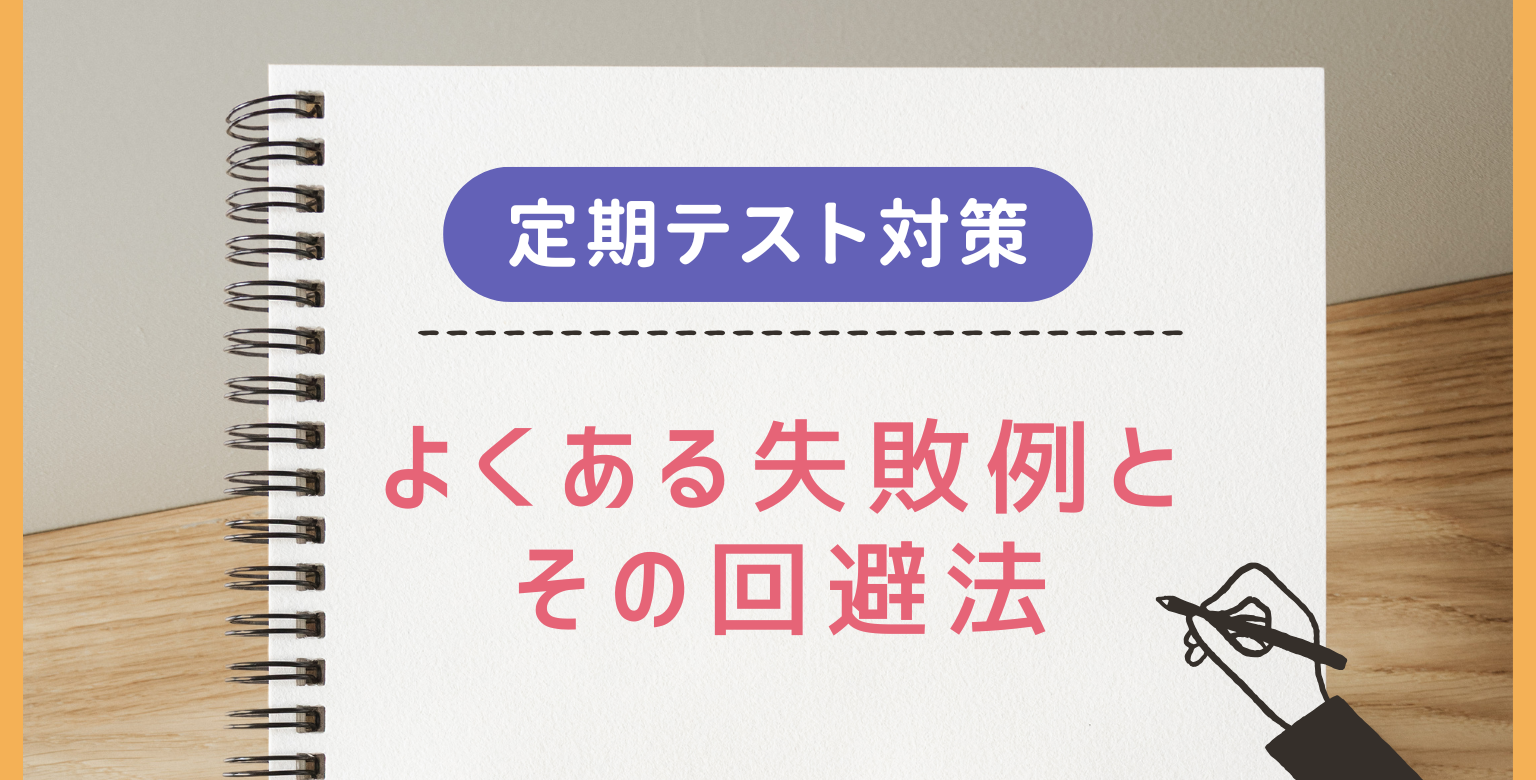
せっかくスケジュールを立てて定期テスト対策に取り組んでも、思うように結果が出ないという声は少なくありません。
その原因の多くは、スケジュール作成や学習の進め方にありがちな「落とし穴」にあります。
ここでは、特に多い失敗例と、それを避けるための具体的な対策をご紹介します。
計画が細かすぎて実行できない
意気込んで時間単位でびっしりとスケジュールを組んだものの、予定通りにいかずに挫折してしまうケースは非常に多いです。
予期せぬ予定や体調不良など、現実は思い通りにならないことがあるため、スケジュールには余白と柔軟性を持たせることが大切です。
1日ごとの細かな短期的計画と、「今週中に数学の問題集を1周」「2週間以内に200語英単語を暗記する」など、中期的計画を併用することをおすすめします。
やるべきことの優先順位をつけていない
全教科を同じように進めようとして、結果的に苦手分野に手が回らなかったというのも、よくあるパターンです。
すべての教科を完璧にこなそうとするのではなく、得点に直結しやすい分野や、反対に苦手で点が取りにくい分野から優先的に着手するなど、戦略的に時間を割り振ることが重要です。
復習を疎かにしてしまう
一度勉強しただけで安心し、復習せずに記憶が曖昧になってしまうパターンです。
特に暗記科目では、学習後24時間以内の復習が記憶定着に効果的といわれています。スケジュールを立てるときは、新しい学習と並行して復習時間も組み込むようにしましょう。
復習には、「見るだけ」「書き出す」「人に説明する」など複数の手法を組み合わせることで、より効果が高まります。
計画倒れでモチベーションが下がる
初日からノルマがこなせず、「もうダメだ」とやる気を失ってしまう人も多く見られます。これは、最初から無理な量を詰め込んでいることが原因の場合がほとんどです。
スタートは軽めに設定し、少しずつペースアップしていくことで、継続しやすくなります。
また、スケジュールは「守るもの」ではなく「調整するもの」と捉え、自分に合ったリズムを探す気持ちで取り組みましょう。
【定期テスト対策】モチベーションを保つための小技
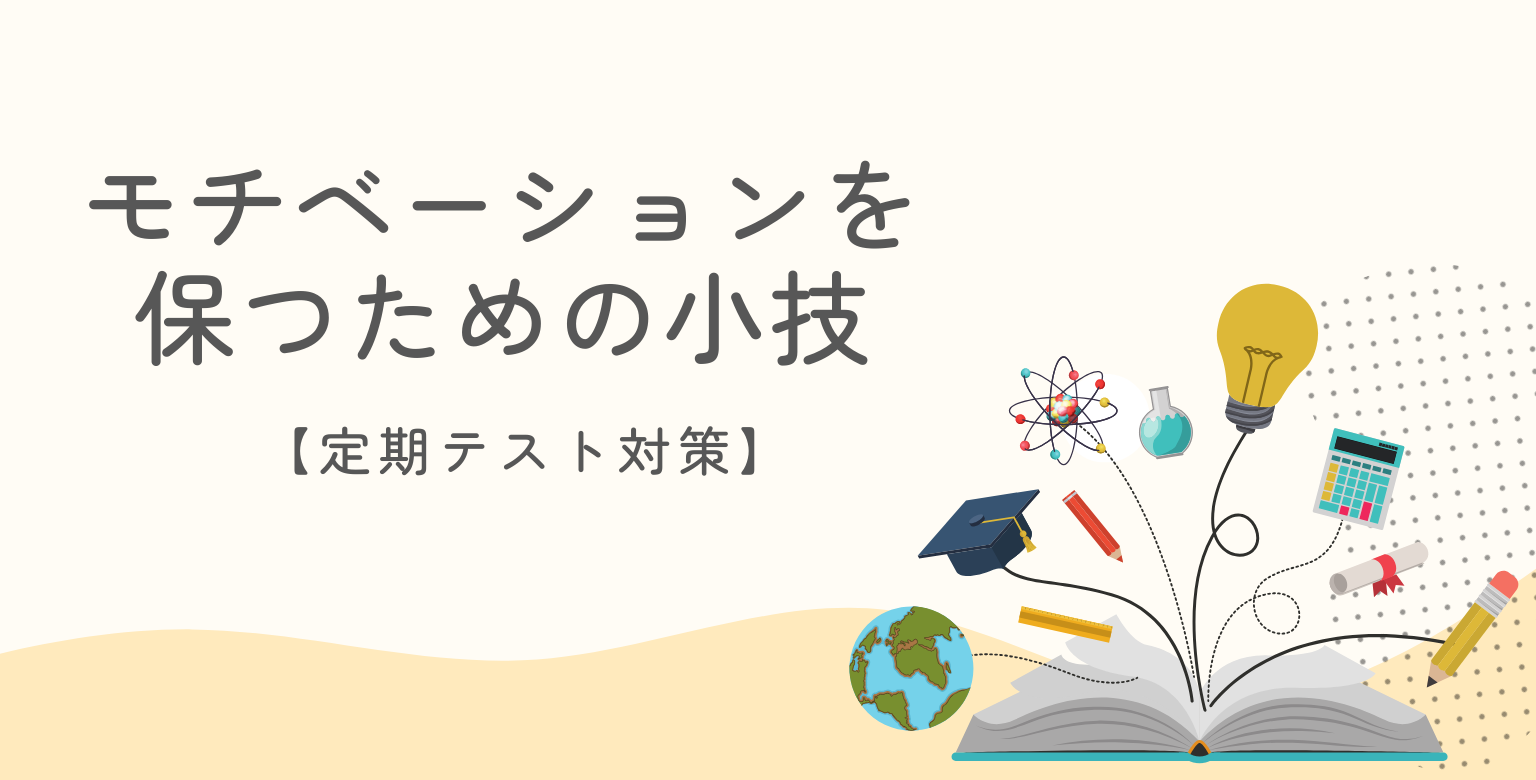
定期テスト対策において、最も難しいのは「やる気を維持すること」です。
ここでは、モチベーションを下げずに勉強を継続するための「ちょっとした工夫」をご紹介します。
目標を「見える化」する
まず大切なのは、目標を具体的に言葉にすることです。
例えば、「英語で80点を取る」「数学の平均を超える」といった目標を紙に書いて、机の前やノートに貼っておくことで、毎日の行動に意味を感じやすくなります。
明確なゴールがあると、自然とそれに向けた行動を意識できるようになります。
やったことを記録する
モチベーションを維持するには、「自分がどれだけ進んだか」を実感することが大切なので、勉強記録をつけることがおすすめです。
手帳やアプリ、ホワイトボードなどに「やったこと」を記録すれば、達成感を得られ、継続する力になります。
勉強場所を変えてみる
同じ場所で同じことをしていると、どうしても気が滅入ってしまうことがあります。そんな時は、思い切って勉強場所を変えてみましょう。
図書館、自習室、カフェなど、場所を変えることで気分もリフレッシュされ、新しい気持ちで取り組めるようになります。また、「時間帯によって場所を変える」といった工夫も効果的です。
定期テスト対策と大学受験対策の両方ができる予備校なら
画像出典:会員制現役予備校BrainsGym
定期テストでしっかりと結果を出しつつ、大学受験に向けた基礎力も同時に身につけたい高校生におすすめなのが、会員制予備校の「BrainsGym」です。
BrainsGymでは、一人ひとりの目標や学力に合わせたオーダーメイドの学習プランを提供しており、学校の定期テスト対策から長期的な受験戦略までを、一貫してサポートしています。
また、個別指導や担任による進捗管理、静かな自習環境など、学び続けやすい仕組みが整っているのも特徴です。
特に、「やるべきことが明確にならない」「計画通りに勉強できない」と悩んでいる高校生にとっては、プロによる伴走が大きな安心感につながります。
定期テスト対策と大学受験対策を両立したい方は、ぜひ一度 BrainsGym をチェックしてみてください。
▶BrainsGymの合格実績と先輩たちの体験談
※すべてBG正会員の現役合格実績です。
まとめ
定期テスト対策で結果を出すためには、単なる努力や時間だけでなく、「計画性」と「自分に合った工夫」が鍵となります。
しっかりとスケジュールを立てることで、無理なく、無駄なく、そして確実に学力を積み上げていくことが可能になります。
地道な積み重ねは、必ず大きな成果となって返ってきます。定期テストを通じて、成績アップだけでなく、将来にもつながる学習習慣と自信を育てていきましょう。
会員制大学受験予備校「BrainsGym(ブレインズ・ジム)」では、AI学習システム「atama+」を活用したBGパーソナルや、弱点克服と得意分野の強化を両立し、学習に集中できる会員制自習室の自分専用個別ブース「BGセルフ」、さらに「プレサポ」と呼ばれる受験コンサルティングなど、最適な学習環境を提供しています。
大学受験対策だけでなく、学校の授業やカリキュラムに準拠した指導も行っており、定期テスト対策や内申点の向上にも強く、指定校推薦や総合型選抜による合格者も多数輩出しています。
教室見学・無料体験は随時受付中ですので、興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。