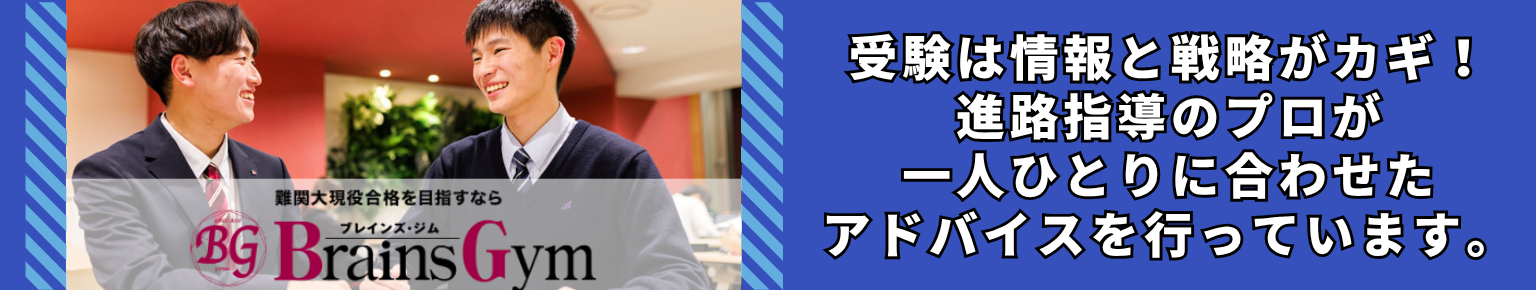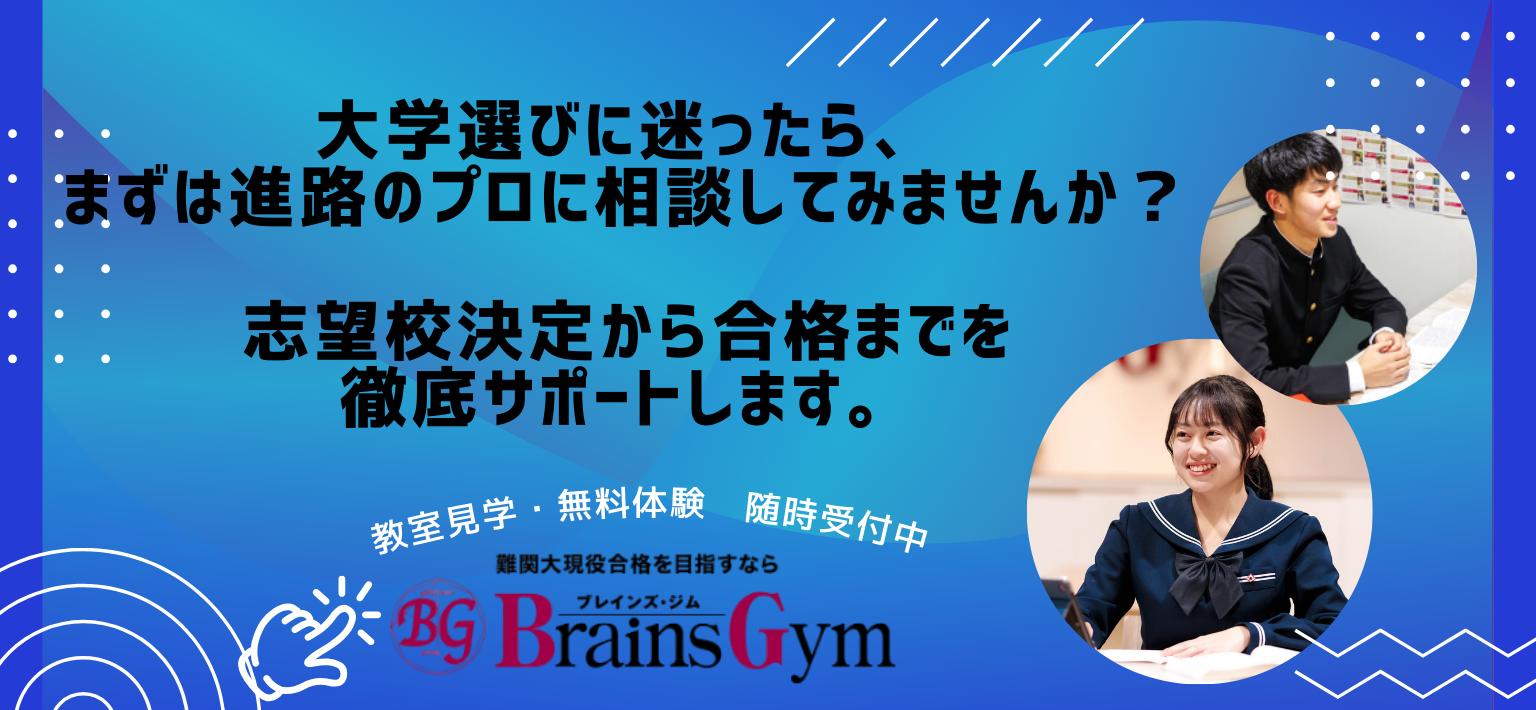2025.08.04
大学の選び方に迷ったら?高校生のための大学の選び方ガイド【保存版】

大学選びは、将来の進路や人生の方向性を左右する大切なステップです。しかし、数ある大学の中から「どこを選べばよいのか」「何を基準に決めればよいのか」と、不安を感じる人も多いかと思います。
本記事では、自分に合った進学先を見つけるためのチェックリストや情報収集のコツ、さらには予備校の活用方法までを丁寧に解説します。
【大学の選び方】重視すること
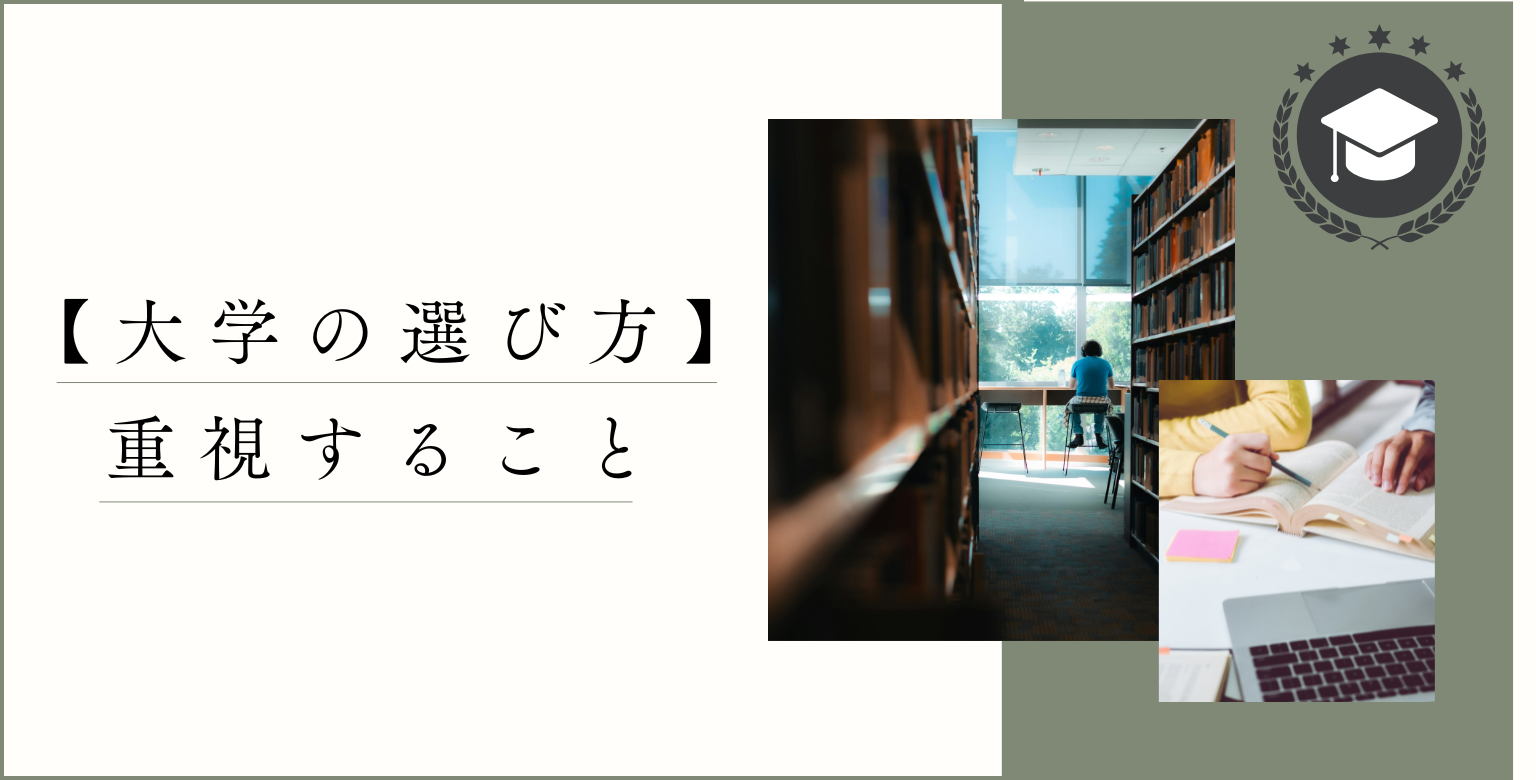
自分に合った大学を選ぶためには、将来の目標や価値観、学びたいことをしっかり考えることが大切です。
ここでは、なぜ「大学選び」が重要なのかを解説します。
大学は将来のキャリアに直結する
大学での学びは、将来の仕事や生き方に直結する重要な要素です。学部や専攻によって学べる内容が異なり、それがそのまま就職先やキャリア選択に影響することも多くあります。
例えば、医療や建築、教育などは専門的な知識や資格が必要な分野であり、進学先の選択が将来の選択肢を大きく左右します。
また、大学時代に得た知識や経験、人とのつながりは、社会に出たときの大きな財産になります。
反対に、自分の興味や将来の目標と合わない大学を選んでしまうと、途中で進路変更を余儀なくされたり、モチベーションが低下したりすることもあります。
「将来どうなりたいのか」「何を大切にしたいのか」を考えながら大学を選ぶことは、人生設計の第一歩だと言えます。
環境や人間関係が人生を大きく左右する
大学生活は、学問だけでなく、生活環境や人間関係による影響も非常に大きいものです。
大学は高校とは異なり、全国各地から集まった多様な価値観を持つ学生と出会える場です。どんな環境に身を置き、どんな人たちと関わるかによって、自分の考え方や将来の視野も大きく広がります。
キャンパスの雰囲気や学生の気質、都市型か地方型か、寮の有無、課外活動の充実度など、学外の要素も充実した大学生活には欠かせません。
また、友人や先輩、教員との出会いが、その後の人生における転機になることも珍しくありません。
進学先の環境をよく調べ、自分が心地よく過ごせるかどうかをしっかり確認することも、大学選びで後悔しないための大切なポイントです。
「なんとなく」で選ぶと後悔する理由
「友達が行くから」「名前を聞いたことがあるから」といった理由で大学を選んでしまうと、入学後にギャップを感じて後悔するケースは少なくありません。
深く考えずに進学先を決めてしまうと、実際に通ってみて「授業がつまらない」「思っていた雰囲気と違った」「やりたいことが見つからない」と感じてしまい、学習意欲が低下したり、最悪の場合は中退につながることもあります。
大学選びは一時的な選択ではなく、今後の数年間、そしてその先の人生にも影響を与える重大な決断です。
「なんとなく」ではなく、自分の将来や価値観としっかり向き合いながら決めることが、後悔しない進路選びにつながります。
【大学の選び方】いつまでに決めるのか

大学選びに明確な「締め切り」はありませんが、受験対策や出願の準備を考えると、高校2年生の終わり頃までに方向性を固めておくのが理想です。
高校3年生になると模試や受験勉強が本格化し、志望校の決定にかけられる時間が限られてしまいます。
早めに学部や学科の興味を絞り、大学の候補をリストアップしておくことで、効率よく対策を進めることができます。
また、学校推薦型選抜や総合型選抜(旧AO入試)を検討している場合は、さらに早い段階での情報収集と準備が必要です。高校1〜2年生の成績や課外活動、志望理由書の作成が重要になるため、遅くとも高校2年生の夏までには志望校をある程度絞っておくのが望ましいでしょう。
とはいえ、「決めるのが遅かったからもうダメ」ということはありません。高校3年生からでも間に合うよう、予備校や先生のアドバイスを受けながら柔軟に対応することも可能です。
大切なのは、自分のペースで焦らず、でも計画的に進めること。早めの行動が、後悔しない進路選びにつながります。
【大学の選び方】基本ステップ

大学選びで失敗しないためには、感覚やイメージだけで決めるのではなく、いくつかのステップを踏んで客観的に判断することが大切です。
将来の目標や興味を見つめ直し、学びたい内容や入試方式、大学の立地などを具体的に検討することで、自分に合った進学先が見えてきます。
ここでは、大学選びの基本ステップについて解説します。
将来の目標や興味を明確にする
大学選びの第一歩は、自分の将来について考えることから始まります。「将来なりたい職業がある」「興味がある分野がある」といった目標がある人は、それに合った学部・学科を軸に大学を探すことができます。
一方、まだ明確な目標がない場合でも、興味のあることや得意な科目、どんな働き方をしたいかといった視点から考えることで、自分に合った方向性が見えてくることもあります。
例えば、「人と関わる仕事がしたい」という人は、教育・福祉・サービス業など多様な進路が考えられます。
高校の進路指導の先生や家族、塾の講師に相談するのも良い方法です。目指す未来が少しでも見えていると、その実現に近づくために最適な大学や学部を選びやすくなります。
学びたい学部・学科を絞り込む
大学には数多くの学部や学科があり、それぞれ専門性の高いカリキュラムが用意されています。自分が何を学びたいのか、将来どんな分野で活躍したいのかを踏まえた上で、学部・学科を選ぶことが大切です。
例えば、心理学に興味があるなら文学部や人間科学部、医療系なら看護学部や保健医療学部など、同じ分野でも設置されている学部名が異なる場合があります。
また、同じ学部名でも大学によってカリキュラムや研究の重点が異なるため、大学のホームページやパンフレットで具体的な授業内容や研究分野をよく確認することが重要です。
興味・関心と学びの内容が一致していれば、大学生活の満足度も高まり、学びへのモチベーションも維持しやすくなります。
偏差値・入試方式を確認する
志望する大学・学部が決まったら、次に確認すべきなのが偏差値や入試方式です。偏差値はあくまで一つの目安ですが、自分の学力と志望校との距離を把握する上で重要な指標になります。
無理のない範囲で「挑戦校」「実力相応校」「安全校」のバランスをとって志望校を設定することが大切です。
大学によっては一般選抜のほかに、学校推薦型選抜、総合型選抜(旧AO入試)があり、さらに私立大では一般選抜の中に共通テスト利用型が存在するなど、さまざまな入試方式があります。
それぞれの入試方式に求められる対策や準備期間が異なるため、自分の得意分野や高校での成績に合わせて選ぶのがポイントです。受験戦略を立てる上でも、早めに情報収集をしておくと安心です。
立地・キャンパス環境を比較する
大学生活は学びだけでなく、生活そのものでもあります。そのため、大学の立地やキャンパスの雰囲気も重要な判断材料です。
都市部にある大学は交通アクセスやアルバイト先が充実している一方で、家賃が高くなることもあります。地方の大学は自然が豊かで落ち着いた環境で学べますが、アクセスの面では制約がある場合もあります。
また、同じ大学でも学部によってキャンパスが異なることもあるため、志望学部がどこにあるのかも要確認です。さらに、キャンパス内の施設の充実度や学生サポート体制、課外活動の雰囲気も大学生活を豊かにする大切な要素です。
実際にオープンキャンパスや見学に行き、自分にとって快適に過ごせる環境かどうかを見極めることをおすすめします。
文系・理系別の大学の選び方ポイント
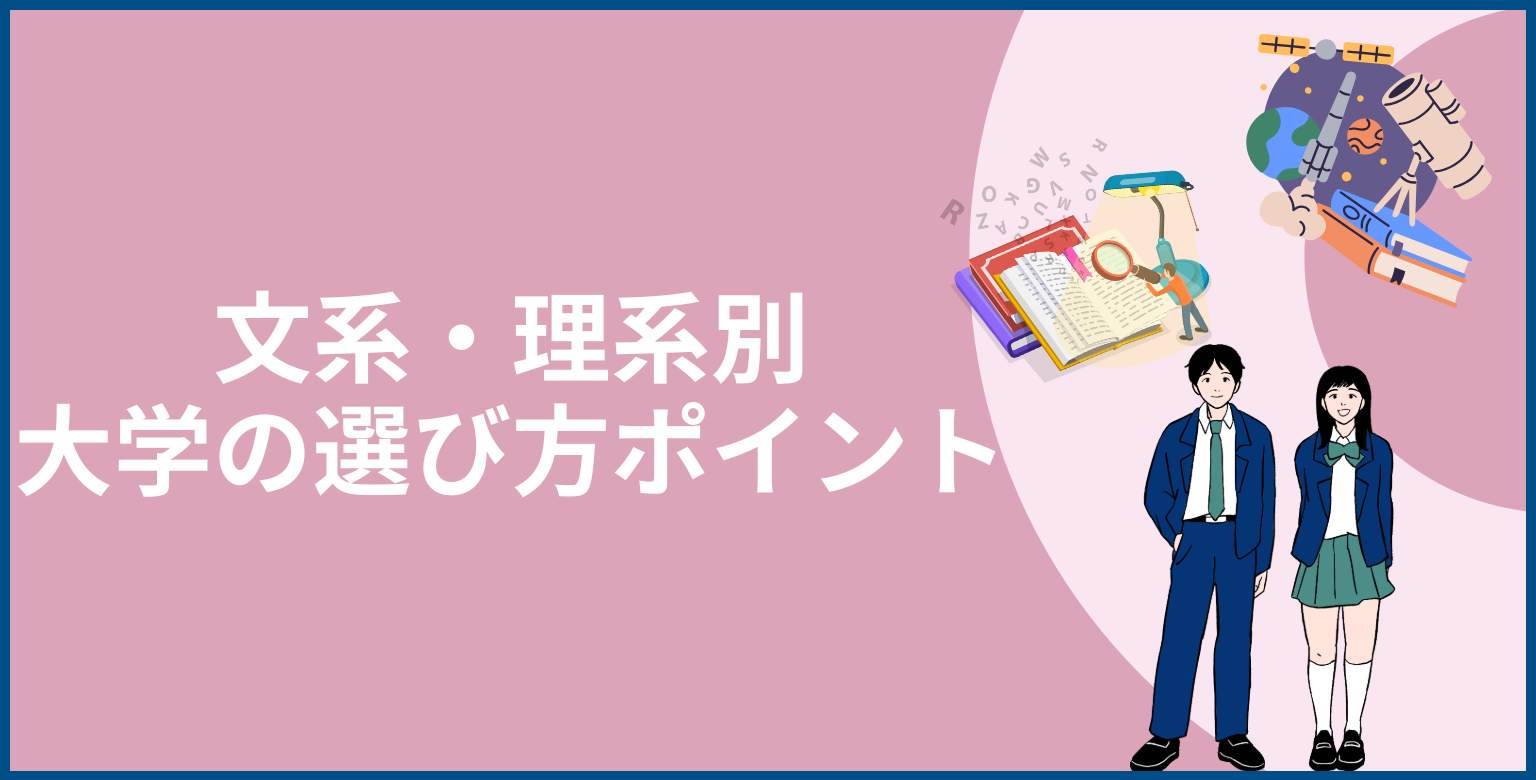
大学選びを進める上で大きな分かれ道となるのが「文系か理系か」の選択です。
それぞれで学べる内容や将来の進路が大きく異なるため、自分の興味や得意分野に合った選び方が重要です。
ここでは、文系・理系それぞれの特徴や向いている人の傾向、迷ったときの判断ポイントについて解説します。
文系に向いている人の特徴と選び方
文系に向いている人の特徴としては、「人の心や社会のしくみに興味がある」「文章を読んだり書いたりするのが得意」といった傾向が挙げられます。
文系学部では、法律、経済、経営、文学、教育、国際関係など幅広い分野を学ぶことができ、卒業後は公務員、営業、企画、教育、出版など多様な業界・職種で活躍できます。
大学選びの際には、カリキュラムの内容に加えて、就職実績やインターンシップのサポート体制も確認してみてください。
また、語学力を伸ばしたい場合は、留学制度の有無や語学教育の充実度にも注目しましょう。自分の得意分野や興味を起点に、将来につながる学びができる大学を選ぶことが重要です。
理系に向いている人の特徴と選び方
理系に向いている人の特徴としては、「数字や理論で物事を考えるのが好き」「科学的な思考が得意」「実験やものづくりに興味がある」といった点が挙げられます。
理系学部では、工学、情報、農学、薬学、看護、理学、医学など専門性の高い知識を学び、研究や開発、技術職などの職業に直結するケースが多くあります。
大学を選ぶ際は、研究施設や実験設備の充実度、教授の専門分野、卒業後の進路(就職か大学院進学か)などをチェックすることが重要です。
また、国家資格の取得が関係する学部では、合格率やサポート体制も比較ポイントになります。理系の学びは専門性が高いため、自分の関心がどこにあるかをじっくり考えた上で選択することが求められます。
文理選択で迷っている場合の考え方
文系か理系かで迷っている人は、自分の得意科目だけでなく、将来やりたいことや興味の方向性から考えてみてください。
例えば、数学は得意でも人と関わる仕事に興味があるなら文系の道も考えられますし、社会や地理が好きでもITやテクノロジーに興味があるなら理系の可能性もあります。
実際のところ、文理の境界があいまいになってきている分野も増えており、例えば心理学や経済学は統計やデータ解析といった理系的要素も含んでいます。
また、大学によっては「総合系学部」や「学際系プログラム」を設けており、文理をまたぐ学びが可能な場合もあります。
迷っている段階では、まずは情報を集め、オープンキャンパスや体験授業などを活用して実際の雰囲気を感じることが判断材料になります。
失敗しないための大学選びチェックリスト
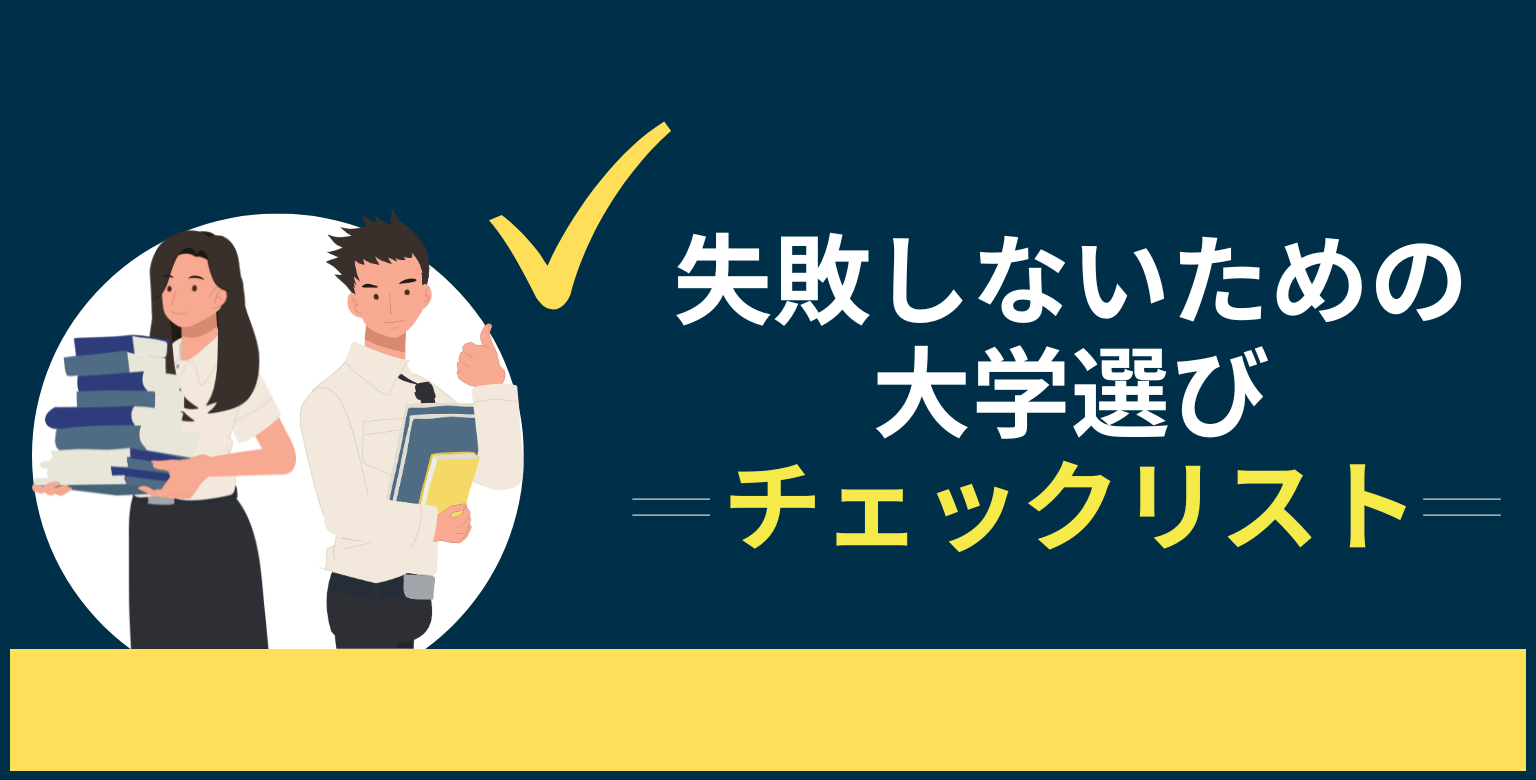
大学選びは人生を左右する大きな選択だからこそ、「なんとなく」で決めてしまうのは危険です。後悔しない進路にするためには、いくつかの視点から自分に合った大学かどうかを見極めることが大切です。
ここでは、大学選びの基本ステップに加えて、大学選びの最終確認として活用できるチェックポイントをご紹介します。
実際に行ってみて雰囲気に違和感はないか
パンフレットやWebサイトで好印象を持った大学でも、実際に足を運んでみると「思っていた雰囲気と違う」と感じることは少なくありません。
キャンパスの広さや設備、学生の雰囲気、教職員の対応などは、実際に見て・聞いて・感じてみないと分からないことが多くあります。自分が心地よく過ごせる環境かどうかは、大学生活の満足度に大きく影響します。
オープンキャンパスや見学会に参加し、模擬授業や学生との交流を通じて、自分がその場で4年間過ごすことをリアルにイメージしてみましょう。ちょっとした違和感が、後々の不満につながることもあるため、「感覚」も大切にしましょう。
家族や先生にも相談しているか
大学選びは自分の人生にとって重要な選択ですが、一人で抱え込まず、信頼できる大人に相談することも大切です。家族は経済面や生活面でのサポートをしてくれる存在であり、進学先を決める上でも大きな影響を与えます。
また、学校の先生や塾の講師は進路指導のプロフェッショナルとして、客観的な意見や情報を提供してくれます。これにより、自分では気づけなかった視点を教えてもらったり、選択に自信が持てるようになったりします。
もちろん最終的には自分の意思で決めることが重要ですが、第三者の意見を聞くことで視野が広がり、納得のいく選択がしやすくなります。
学費・奨学金制度を確認しているか
大学にかかる学費や生活費は、進学後の生活に大きく関わる現実的な要素です。国公立と私立では学費が大きく異なり、医療・芸術系などは特に高額になる傾向があります。
家族としっかり相談し、無理のない範囲で進学できるかを確認することが大切です。また、奨学金制度や授業料減免制度がある大学も多いため、自分が対象となる制度を早めに調べておきましょう。
制度によっては出願時に申請が必要な場合もあるため、情報収集は早めが鉄則です。経済的な不安を少しでも減らし、安心して学べる環境を整えることが、大学生活の充実にもつながります。
自分の性格や学び方に合っているか
大学には、それぞれ独自の校風や教育スタイルがあります。自由度が高く、自主性を重んじる大学もあれば、少人数制で手厚くサポートしてくれる大学もあります。
どちらが合っているかは、自身の性格や学び方によって異なります。
例えば、自分で計画を立てて学ぶのが得意な人は大規模な大学でものびのびと学べるかもしれません。一方で、サポートが充実している方が安心できる人には、アットホームな環境の大学が合うかもしれません。
過去の自分の学びのスタイルを振り返り、自分に合った環境を選ぶことが、学習成果を上げるカギになります。
最終は自分の意思で決める
大学選びは、家族や先生の意見も参考にしながら行うものですが、最終的には「自分がどうしたいか」が一番大切です。
他人の期待や世間のイメージに流されてしまうと、後悔する可能性が高まります。自分の価値観、興味、目標を軸にして選んだ大学であれば、多少の困難があっても乗り越える力になります。
情報を集め、悩み、比較しながら、自分で決断したという経験そのものが、大学入学前の大切な成長のプロセスになります。
迷うことも多いかもしれませんが、「納得して選んだ」という実感を持てるよう、自分の声にしっかり耳を傾けましょう。
大学の情報収集のコツ

後悔しない大学選びをするためには、正確で多角的な情報を集めることが欠かせません。パンフレットや公式サイトだけでなく、実際の雰囲気を知るためのオープンキャンパスや、在学生・卒業生の声なども有益な情報源です。
ここでは、効果的な情報収集の方法をご紹介します。
大学パンフレットとWebサイトの活用
大学のパンフレットや公式Webサイトは、最も基本的かつ信頼性の高い情報源です。
パンフレットには、学部・学科の概要、取得可能な資格、就職実績、年間スケジュール、施設紹介などがコンパクトにまとめられており、大学全体の特色をつかむのに適しています。
一方、Webサイトは情報の更新頻度が高く、入試情報やイベント案内、学生インタビューなど、リアルタイムでの情報が得られる点が魅力です。
また、大学によっては模擬授業の動画やオープンキャンパスのレポート、研究室紹介なども掲載されており、興味のある分野がどのように学べるのかを具体的にイメージする手助けになります。
複数の大学の情報を比較しながら、自分に合う大学を絞り込む材料として活用しましょう。
オープンキャンパスで見るべきポイント
オープンキャンパスは、大学の雰囲気を実際に体感できる貴重な機会です。写真や文字では分からない「空気感」や「居心地のよさ」を感じるためにも、できるだけ足を運ぶことをおすすめします。
見るべきポイントとしては、まずキャンパスの施設や設備の充実度。図書館や食堂、実習施設などを見学し、自分が学ぶ環境として快適かを確認しましょう。
また、模擬授業に参加し、教授の教え方や講義内容が自分に合っているかどうかもチェックしたいポイントです。
学生スタッフの雰囲気や質問対応の丁寧さからも、大学の風土が垣間見えます。可能であれば複数の大学を訪問して比較することで、自分にフィットする大学像がより明確になります。
在学生・卒業生のリアルな声を聞く
大学選びで迷ったときに参考になるのが、実際にその大学に通っている在学生や卒業生のリアルな声です。
パンフレットやWebサイトには載っていない「本音」や「裏話」を知ることで、より現実的な視点で大学を評価することができます。
在学生に話を聞くには、オープンキャンパスでの個別相談や学生スタッフとの交流、学校紹介イベントなどが有効です。
質問の仕方としては、「どんな授業が印象的だったか」「就職支援はどうだったか」「課外活動の雰囲気はどうか」など、具体的なエピソードを引き出すようにしましょう。
また、卒業生の進路や就職先を調べることも、その大学が自分の将来につながるかどうかを判断する材料になります。リアルな声を取り入れることで、納得度の高い大学選びが可能になります。
大学選びと予備校の活用
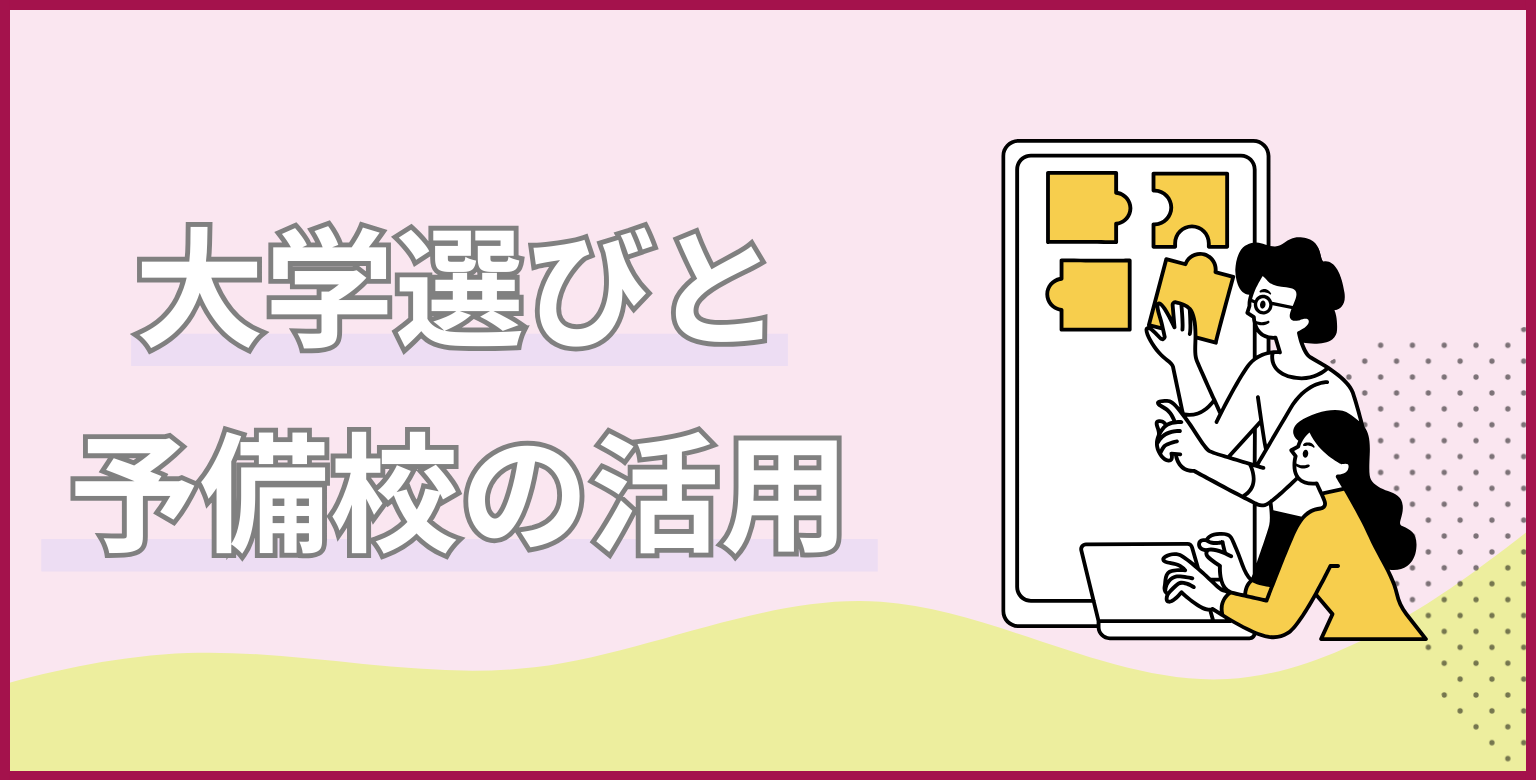
大学選びや受験対策を一人で進めるのは、不安が多いものです。そんなときに頼りになるのが、進学塾や予備校の存在です。
学力の向上はもちろん、最新の受験情報や進路相談、大学選びのアドバイスまで、多角的にサポートしてくれます。
ここでは、予備校の効果的な活用法をご紹介します。
予備校を活用するメリット
大学受験は「情報戦」とも言われるほど、入試制度や出題傾向の変化に対応することが重要です。予備校を活用する最大のメリットは、そうした最新情報を踏まえた学習指導や進路サポートが受けられる点にあります。
また、限られた時間の中で効率よく学習を進めるためには、プロの講師による的確な指導が不可欠です。志望校ごとに出題傾向を分析したカリキュラムや教材が用意されており、自分の弱点を的確に補強することができます。
さらに、同じ目標に向かう仲間と切磋琢磨できる環境は、モチベーションの維持にもつながります。家庭学習では得にくい学習のリズムや適度な緊張感が持てるのも、予備校ならではの魅力です。
個別指導や情報提供のサポートが受けられる
予備校によっては、集団授業に加えて個別指導や進路相談の体制も整っており、自分に合った学習方法で取り組むことができます。
特に個別指導がある場合は、生徒一人ひとりの学力や志望校に応じたカリキュラムをカスタマイズできるため、苦手科目の克服や志望校対策がより効果的に進みます。
また、予備校は大学の入試傾向や倍率、出願スケジュールなど、最新かつ詳細な情報を常に把握しているため、自分だけでは調べきれないような情報もスムーズに得られます。
模試の結果をもとにした進路アドバイスや、出願先の戦略立てなど、専門スタッフのサポートを活用することで、より現実的で合格に近づく選択が可能になります。
「BrainsGym」なら大学選びも合格も徹底サポート!

画像出典:BrainsGym
高校生のための会員制予備校「BrainsGym」では、大学選びから合格までを一貫してサポートする体制が整っています。
進路指導のプロによる個別カウンセリングでは、生徒一人ひとりの興味・関心・将来像を丁寧にヒアリングし、最適な大学・学部選びをお手伝いします。
さらに、志望校のレベルや特性に応じた学習プランを作成することで、無駄のない受験対策が可能になります。また、生徒のライフスタイルに合わせた柔軟な学習スタイルも魅力の一つです。
また、早稲田・MARCH・東京理科などの有名私大が、BrainsGymのためだけに合同説明会を実施する「有名私大ガイダンス」や、現役大学生のBrainsGym講師たちが自分の通う学部の魅力やリアルな大学生活を紹介する「学部フォーラム」など、進路選択に役立つイベントも多く開催しています。
受験情報の提供だけでなく、学習習慣の定着やモチベーション維持のためのサポート体制も万全です。迷いがちな大学選びの悩みも、安心して相談できる環境が整っています。
まとめ
大学選びは、将来の人生を大きく左右する大切なステップです。学びたいこと、将来の目標、キャンパスの雰囲気、学費やサポート体制など、さまざまな視点から「自分に合った大学」を見極めることが重要です。
情報を集め、家族や先生のアドバイスも参考にしながら、最終的には自分の意思で納得のいく選択をすることが、後悔しない進路選びにつながります。
とはいえ、一人で判断するのが難しいと感じることもあるはずです。そんなときは、会員制大学受験予備校「BrainsGym(ブレインズ・ジム)」のような、プロのサポートを活用するのがおすすめです。
「プレサポ」と呼ばれる受験コンサルティングでは、丁寧な進路相談に対応。さらに、AI学習システム「atama+」を活用した個別最適型指導「BGパーソナル」や、弱点克服と得意分野の強化を両立できる自習環境「BGセルフ」(会員専用の個別ブース)など、最適な学習環境が整っています。
大学選びから合格までを一貫してサポートし、一人ひとりに合った未来を切り開くために、全力で応援しています。
教室見学・無料体験は随時受付中ですので、興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。